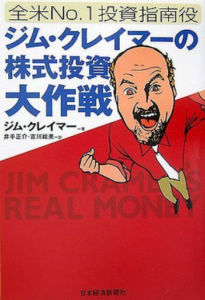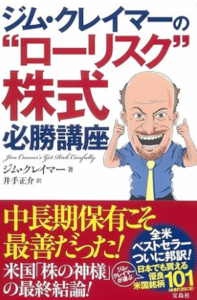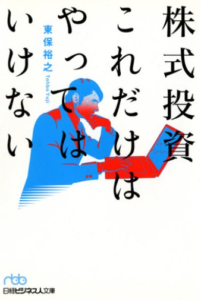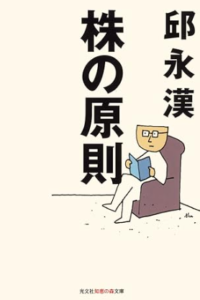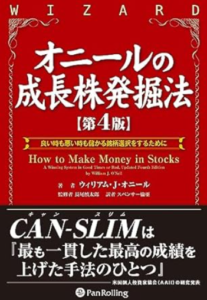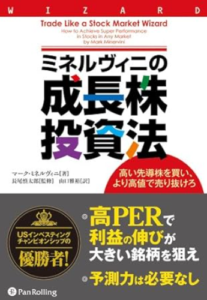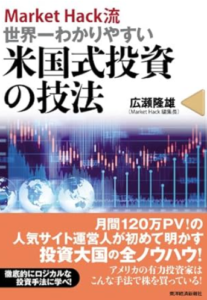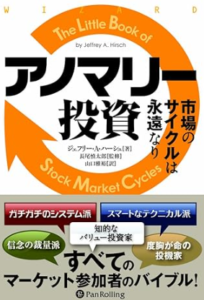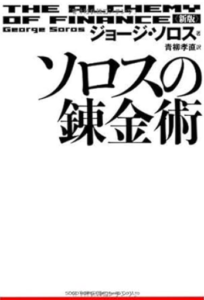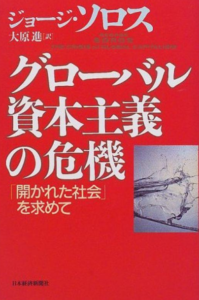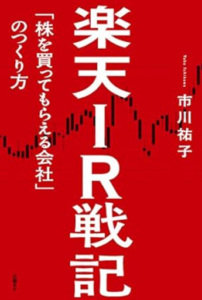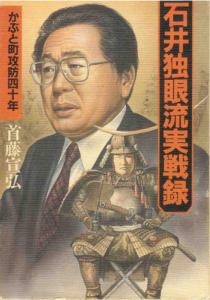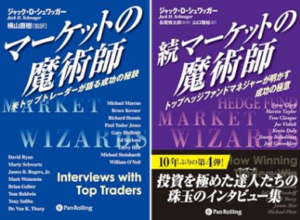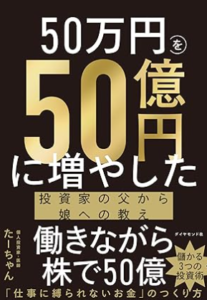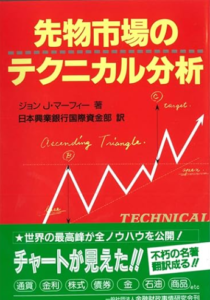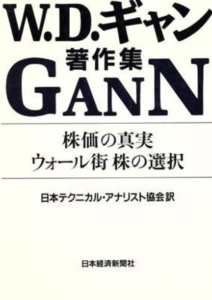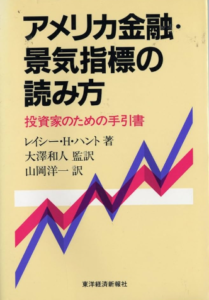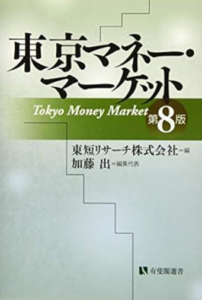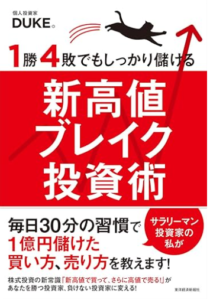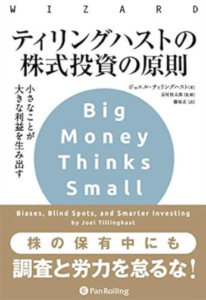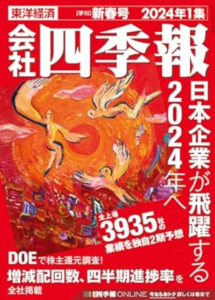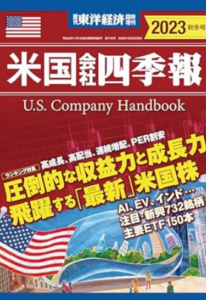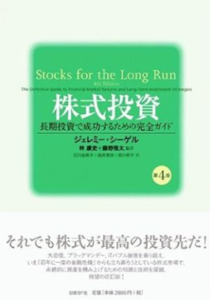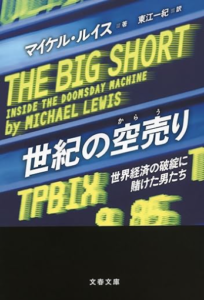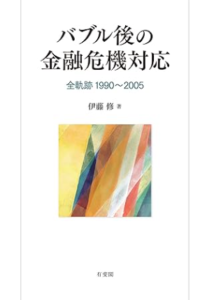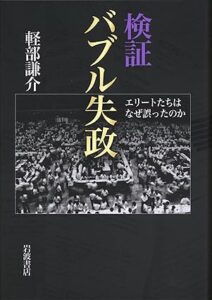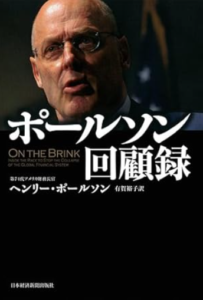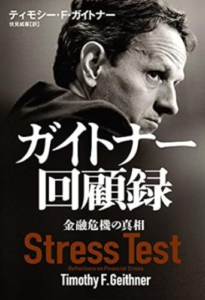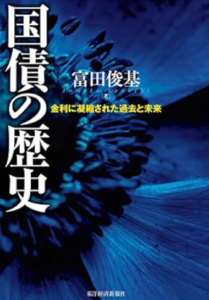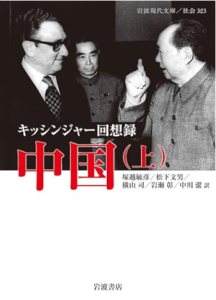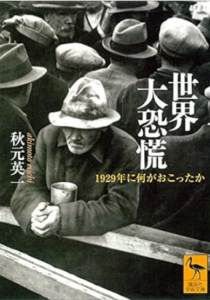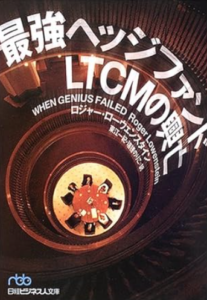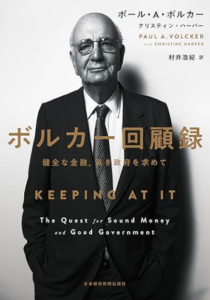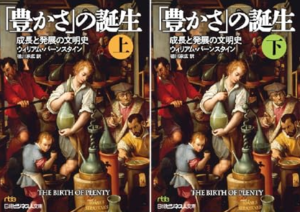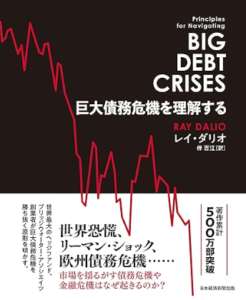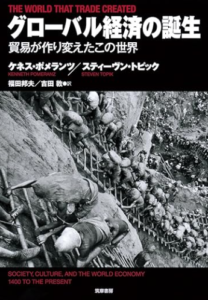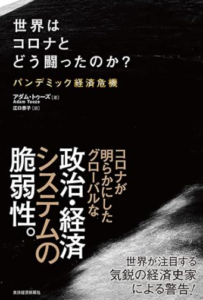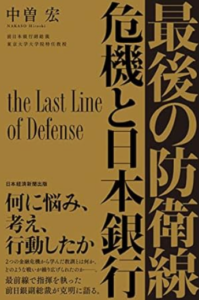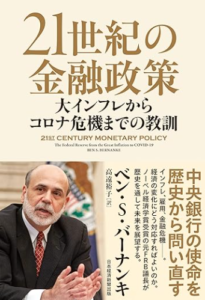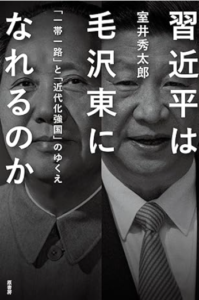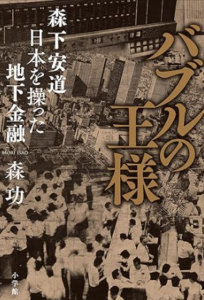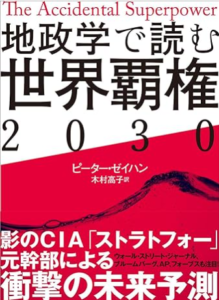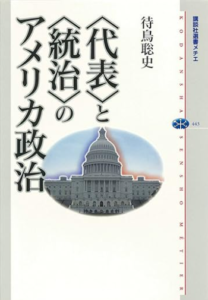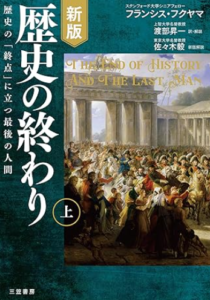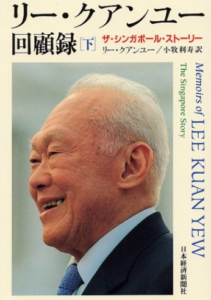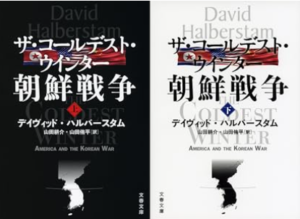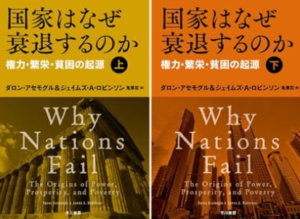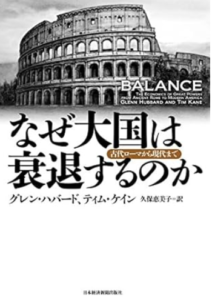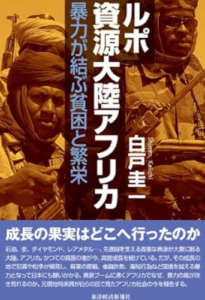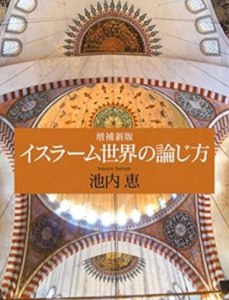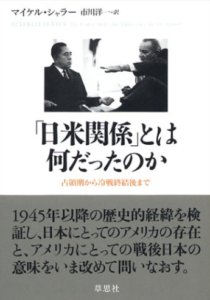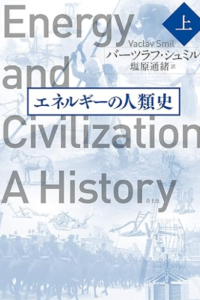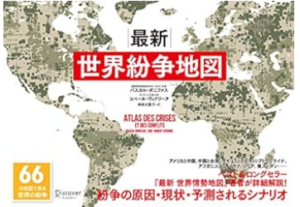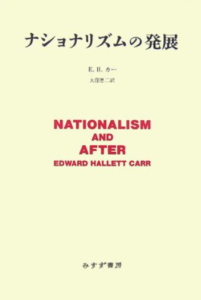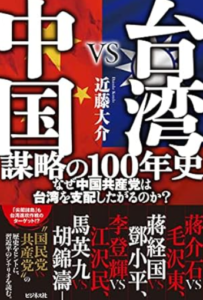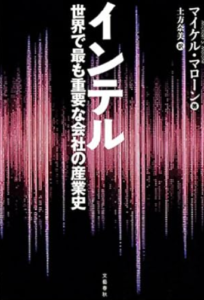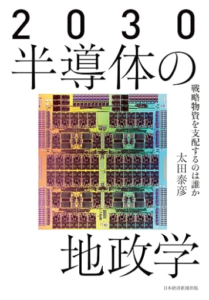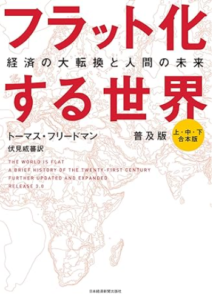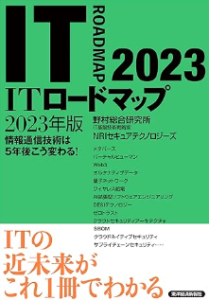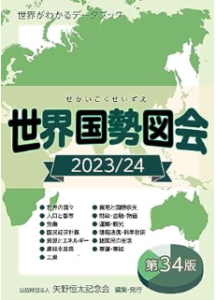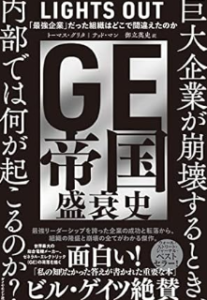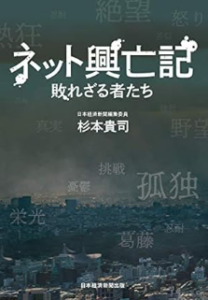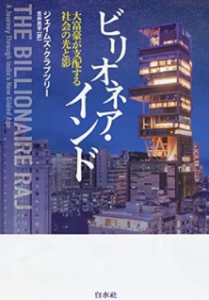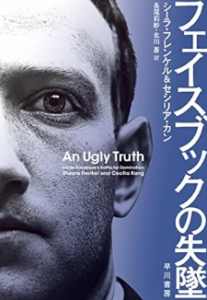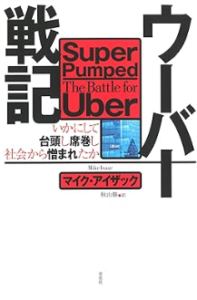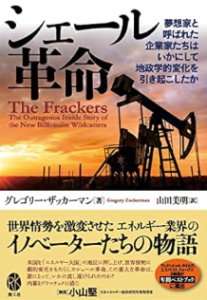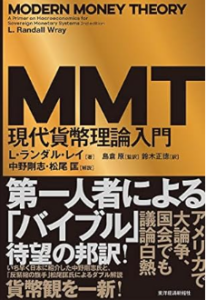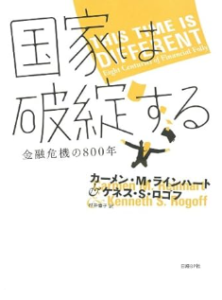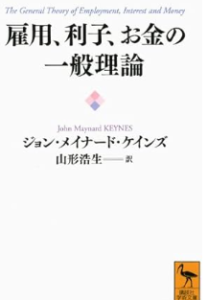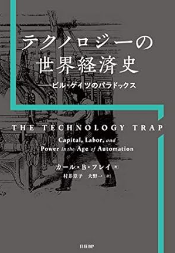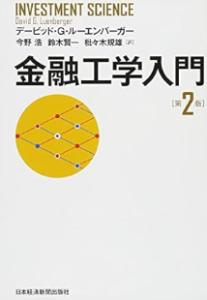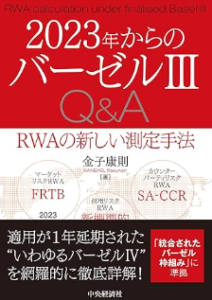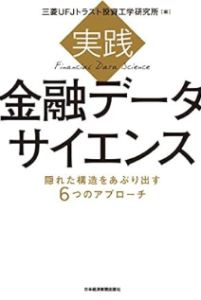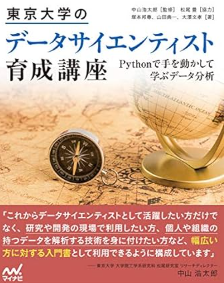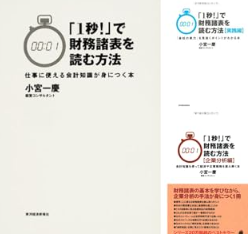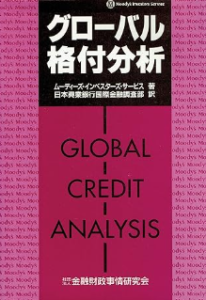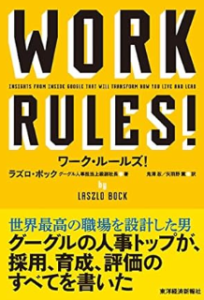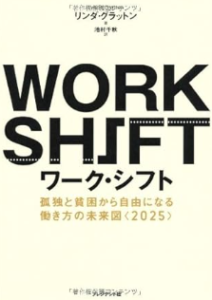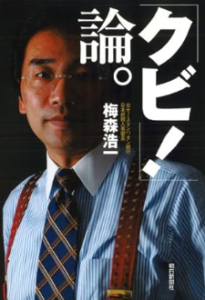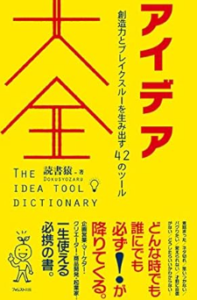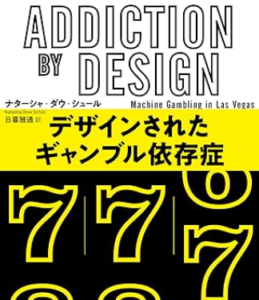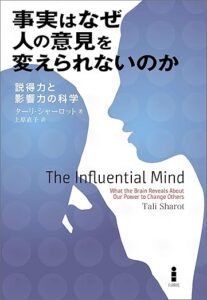お薦め書籍の一覧を掲載しておきます。投資は実践して学ぶだけではなく、様々な書籍も読みながら知識も蓄えていくことを並行して行うと効率的。書籍の画像およびリンクをクリックするとAmazonのページに飛ぶようにしてあります。
また以下のようなカテゴリ分けをしていますので下記リンクをクリックするとそのカテゴリ欄までジャンプします。
<投資指南・哲学書籍>
<ファンダメンタルズ・テクニカル分析関連書籍>
<金融事件史・歴史関連書籍>
<国際政治関連書籍>
<業界・経済勉強関連書籍>
<アカデミック系(金融基礎知識など)>
<プログラミング系>
<財務分析関連>
<不動産投資・中古マンション売買関連>
<その他自己啓発系>
| 個人的にはこれより優れたテクニカル分析の本を読んだことがなく、初心者から上級者までテクニカル分析の基礎を知る上で必要不可欠な一冊だと思っている。 | |
| テクニカル分析の古典かつ金字塔的な書籍。「先物市場のテクニカル分析」と併せて読めばテクニカル分析の勉強は十分と個人的には思っている。 | |
| 相場サイクルについては、プロもこれを下地にレポート書いてるだとか。 とりあえずこの一冊を読めば相場サイクルの知識については間違いない。 | |
| ネット企業が増加していくことによって従来のPERやPBRでは企業バリュエーションを評価していくのに限界を迎える中で、どのようにハイパーグロース株の企業評価は計算されているのかがわかる一冊で、グロース株をきちんと分析して投資したいという投資家は読んでおきたい一冊。 | |
| 投資家として著名な高橋亀吉先生の自伝だが、生涯において何回も経済を分析する上で構造変化とともに古い経済理論を捨て、新しい考え方を取り入れているのを見ることができ、古い考え方に固執するのは間違っていることがわかる。 | |
| バフェット氏が師と崇めるベンジャミングレアム氏の分析手法の集大成。バリュー株投資家にとっては絶対に一度は読んでおきたい一冊。 | |
| プライベートエクイティファンドの拡大につれてスタートアップがそもそも企業拡大において調達資金を使い切って成長し、その後再度資金を調達することが前提となっていることがわかる一冊。グロース株もこれに近い状況が起こっているように思える。 | |
| かなり古い書籍だが、米国のどの景気指標を見るのがもっとも効果的なのか、景気サイクルをどう読むのかがわかりやすく書いてある一冊で、買えるなら絶対手元に欲しい一冊。 | |
| 一通り見るべき世界の経済指標が網羅されている書籍で、プロかけだしの人とかは勉強がてら読まされる一冊で金融市場を予測する上で知らなければいけない指標の基礎の基礎は全て網羅されている書籍。 | |
| ほとんどの投資家にとってはなじみのないマネーマーケット関連書籍。金融クラッシュが来るときは必ずこの短期市場が荒れるので、知っておいて損はないと思う。 | |
| グロース株を追いかける際に役に立つ考え方。攻めを意識した投資の仕方なので、損切りをしっかりできる方ならば大いに参考になる投資手法だと思う。ややミネルヴィニ氏の書籍と内容は被っている。 | |
| 原油・貴金属・非鉄金属における先物取引と価格変動のメカニズムについてあますことなく網羅しているコモディティ取引手掛ける人は絶対読んでおいて欲しい一冊。 | |
ティリングハストの株式投資の原則 ーー小さなことが大きな利益を生み出す |
2022年の下げ相場を体感した後読むと、投資初心者が知っていなければいけないことがたくさん書いてあったので推薦図書と認定。 ちなみに実質的にレバナスが害悪とも書かれている。 |
|
|
全ての経済・金融市場分析はアメリカからであり、じゃあどうアメリカ経済を理解すればいいのかという第一歩を始める書籍としてぴったりだと思う一冊。 |
会社四季報 |
日本株で個別株投資をするなら四半期毎に発行されている会社四季報の全銘柄に目を通すことは必須作業。スクリーニングして、自分が投資したいと思う銘柄に付箋を貼ってモニタリングしていくと、投資の質は工場すると思う。 |
|
|
日本語で米国株個別銘柄をひとまとめで見れる優れた書籍であり、米国個別株投資をするなら半年に一回発行される先書籍よ読んでおくことは重要。 |
脱「中国依存」は可能か 中国経済の虚実 |
2023年時点の中国経済の問題について、ほぼ重要な部分は全て網羅されている素晴らしい分析書籍であり、2023年時点の中国経済の問題点について知りたい人は必読である分析書籍。 |
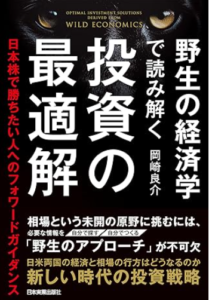
|
最近Youtubeで経済・相場解説で活躍している岡崎良介氏の書籍で、中央銀行(主にFRB)のフォワードガイダンスに関する緻密な分析と、日銀の今後の政策見通しについて書かれた書籍で、今後の金融政策を考える上で重要なアイデアがたくさん詰まっていて勉強になった。 |
|
|
相場の歴史に加えて、投資初心者が考慮すべき相場の仕組み的なものを触りの部分をおおむねさらった内容で、とっつきやすい書籍だったので投資初心者にお薦めしておきたい。 |
| 映画にもなった「マネーショート」の邦訳。多くの裸ショーターは綺麗にショートを決めたいと思っているようだが、実際にこの書籍で出てきたショートで巨額の利益を得た人達も示現するまではじりじりと焼かれていたのがわかる。 | |
| 日本のバブル崩壊時に起こったことと、政治や金融がどのように対処行動をし、それがどのように間違っていたのかを克明に記載した書籍で、バブル崩壊対処はどのように行えばよかったのかを考察させられる良書。 | |
|
|
日本のバブル崩壊から再生までに具体的にどういうイベントが起き、政府・日銀はどのように対応してきたかが詳しくわかる書籍で、不動産バブル後の苦しい軌跡がわかる良書。 |
|
|
よく日本のバブル崩壊の話は崩壊している最中の話がメインだったりするが、こちらの書籍はその前段階の部分にフォーカスした書籍で、バブルにつながった背景をきちんと書いていて良い書籍だと思いました。 |
| リーマンショックの時の原因である税金投入が遅れた経緯はポールソン回顧録を読めば大体わかる。 個人的にはこの書籍以上にサブプライム金融危機中、各プレイヤーがどのように動いたのか理解できる書籍はないと思っている。 | |
| 上記ポールソン回顧録と並んでリーマンショック対応にあたった当事者の回顧録。当時の当局の人達の回顧録で当時の対応の問題点を学んでおきたい。 | |
| ポールソン回顧録・ガイトナー回顧録と併せてリーマンショック対応時の当局者3人衆の一人であり、FRB元総裁の回顧録。上記3冊を読めばリーマンショックの振り返りについてはほぼ完ぺきだろう。 | |
| 過去の景気バブルでどのように人間は狂気に陥っていくのかを書いた歴史書。現代以前のバブルを振り返るにはこの一冊を読むのが良いと思う。 | |
| 様々な国の国債金利を国債が発行されるようになった昔から歴史とともに追えることのできる名著だと思う。 国債金利動向を知らずして相場は語れない。 | |
| 今の米中関係を見るにあたってはピンポン外交して米中間国交を開いた時期の歴史を知ることは欠かせないと思う。 ピンポン外交の立役者でもあるキッシンジャーの回顧録は絶対に読むべき書籍と思う。 | |
| 株価および景気が長期低迷した時期として1929年以降の世界大恐慌だが、あの時はなぜあれほど景気低迷が長期化したのかを知るには一度読んでおきたい一冊。 | |
| クオンツ系がやらかして相場の崩壊を引き起こすようになったのはこのLTCMが先駆けだったように思える。LTCMを知らない方はぜひともこの書籍を読んで勉強してほしい。 | |
| ギリシャショック時のギリシャ財務大臣のヤニスバルファキスの回顧録。EUの財政統合なしの通貨統合の矛盾がいかに深刻で、ギリシャショックの時にギリシャに課せられた緊縮策が厳しいものだったか、どれだけ激しい政治闘争が行われたがわかる一冊。 | |
| 前日銀総裁である白川氏の回顧録。中銀総裁回顧録を読むと、なぜあの時あのような金融政策を取ったのか理解をすることができるので、こういう回顧録はぜひとも読んでおきたい。 | |
|
|
インフレファイターとして米国高インフレ時に果敢に苛烈な金融引き締めを行ったFRB議長として名を馳せたボルカー氏の回顧録で、あの当時何が起きていたかを知ることは非常に重要。 |
| 私有財産権と近代的資本市場が密接に関わっていることがわかる書籍で、逆に言えば歴史的に豊かさを発展するために必要な要素が欠けているような国の株価は最終的には中長期投資ができないことがわかる。 | |
なぜ近代は繁栄したのか――草の根が生みだすイノベーション |
近代の繁栄条件を歴史から読み解いていったもので、逆に未だにそういった条件を満たせないような国には株式投資をしてはいけないというのがわかる、投資基本書の一冊と言えるだろう。 |
巨大債務危機を理解する |
世界的に有名なヘッジファンドであるブリッジウォーターハウス・レイダリオ氏の政府債務の歴史について書いた書籍で、機関投資家といったプロも読んでいる一冊。今一度政府債務について考える上では絶対に読んでおきたい。 |
| 投資に役立てる形で世界の歴史を本当に勉強しておきたいなら中央公論社の世界の歴史の20-30巻をぜひとも全部読んでほしい。この10巻を読むだけでカントリーアロケーションの選び方が変わってくるだろう。 | |
グローバル経済の誕生: 貿易が作り変えたこの世界 |
現在の世界の姿は欧州での飽くなき資源・食料・ぜいたく品需要を背景に活発化した貿易にあることがわかる一冊。 |
|
|
世にも珍しい日本人が国際機関の要請の下に、新興国の中央銀行総裁に就任した話。実務的な話がたくさん書いてあり、新興国はどういった点が経済のボトルネックになっているのかわかり、特にかつて植民地であった新興国の構造的な問題が浮き彫りにされており、フロンティア国に投資する際には読んでおきたい一冊。 |
世界はコロナとどう闘ったのか?―パンデミック経済危機 |
2020年のコロナウィルス暴落に伴ってどのように世界経済は反応し、各国政府と中央銀行はどのような対応策を出したのかを振り返る書籍として、よくまとまっているので、歴史書として残しておきたい。 |
|
|
実際にリーマンブラザーズの従業員が当時社内でどうリーマンブラザーズは暴走したのかが書かれている回顧録。読むと従業員の中でもこれはまずいことが起こると考え、株を売り抜けている人がおり、爆心地に近い人間ほど事情を知っていて暴落回避のための売りをしていることがわかる一冊。 |
|
|
元日銀副総裁の中曽氏の回顧録。日本のバブル崩壊の時とリーマンショックの時に、政府と日銀がどのように動いたかがわかる一冊で、当時を振り返るのにちょうどよいと思う。 |
|
|
前FRB議長であるバーナンキ氏が過去のFRBの金融政策を振り返りながら、リーマンショック以降の非伝統的金融政策やFRBのコミュニケーションスタイルの変化について書いた書籍で、現代のFRBを理解するには必須な一冊。 |
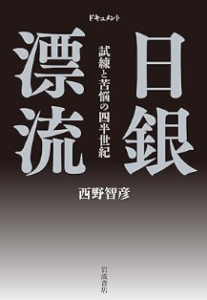
|
日本のバブル崩壊から黒田時代までの日銀の金融政策に関する内部のゴタゴタと政治的圧力を書いた書籍で、バブルが崩壊した時に実際に中央銀行・政府がすんなり対策を打てない理由がわかる良書。 |
|
|
中国を理解するには色々歴史書籍を読む必要性があるが、時間がないとなった時に習近平政権がなぜこれほど経済的に追い詰められるようになったのか・中国株投資を再開する上で見るべきポイントはどこかを考える上ではこの書籍を読むのが良いと思う。 |
|
|
セラノスという一時期最初年女性スタートアップCEOで史上最大規模の企業価値を喧伝されていた企業があったが、実は最初から全てが嘘な上に企業文化もでたらめであったという、なんでこれを投資・出資していた人達は全く見抜けなかったのかという不思議極まる話で、低金利時代にどれだけ皆が金儲けに目がくらみ、何もデューデリジェンスをしていなかったがわかる一冊で、PE投資に関して再考させられる良書だろう。 |
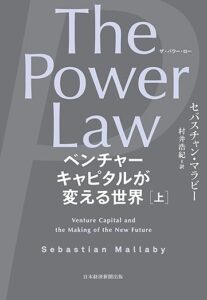
|
ベンチャーキャピタルが世界を変えているという話より、過去のVCの投資スタイルがどんどん高速化していき、最終的に孫正義氏が登場したあたりでも雑なデューデリでいかに早く投資するかに切り替わっていったかという形で、VCやPEの投資姿勢が明らかに変化したことがわかる良い書籍でした。 |
|
|
おそらく漫画・金と銀のいくつかのシーンのモデルになった話がいくつも見られて、日本のバブルに向かう中で暗躍したバブルマネーの動きとその派手さがなんとなくわかる一冊でした。 |
| 地政学リスクを分析する上で、なぜ米国とロシアが絶対的に有利な立ち位置にいるかを理解するのに必須な一冊だと思う。投資において地政学リスクを理解することは非常に重要。 | |
|
|
アメリカはなぜ覇権国家たる資格があるのか・なぜまだ当面覇権国家を維持できるのか・逆になぜ中国は覇権国家となれないかもきちんと理論だって書かれていて、すぐにドル覇権が終わるという言説が現実世界を理解していない妄言であることがすぐにわかる書籍で、地政学を考える上で必読の書籍。 |
|
米国大統領がどれだけ政治への影響力を発揮できるのか、大統領と議会のパワーバランス、そもそも米国政治の構造とはどうなっているのかを認識しておきたいと思う方にお薦めの一冊。 |
|
|
新版 歴史の終わり〔上〕: 歴史の「終点」に立つ最後の人間 |
フランシスフクヤマ氏の代表作で、ソ連の崩壊によって社会主義が崩壊し、民主主義こそが人類が国を統治する最終着地点であることを主張した書籍。しかし、それ以降中国の台頭と先進国での格差拡大に伴うゆらぎから、欧米民主主義の万能性が薄れ、次なる政治の形態を考える必要性が出ている。 |
|
フランシス・フクヤマ氏の「歴史の終わり」に次ぐ代表著作。フクヤマ氏のフランス革命以降の歴史の知見について書かれており、投資と密接に関係する近代政治について考えるなら絶対に読んでおきたい一冊。というよりフランシス・フクヤマ氏の書籍も読んだことがないのに近代政治を語ること自体が間違っていると言ってもいい。 |
|
|
米国が先進国の中でも国の成り立ちからして相当程度異なり、その国の成り立ちから反エスタブリッシュメントの気概が非常に強く、それがチャレンジ精神や反骨精神を生む原動力になっていることを書いた一冊。米国文化を知りたいなら森本あんり氏の書籍をいくつか読んでみるとよいだろう。 |
|
|
世界の中でも未承認国家で紛争が起き、それがリスクオフの引き金になることがしばしばある。そのため、未だ紛争の火種になりかねない地域を知っておくことはグローバルに投資する人にとっては重要。 |
|
|
下巻のみの推薦。上巻はほとんどシンガポール建立の話しかないので、シンガポールに興味ある方しか読む価値がないが、下巻では小国シンガポールが生き残るために、常に世界情勢に気を配っていたリークアンユーが各国・地域ごとの情勢について事細かく記述しており、当時の戦後~2000年手前ぐらいまでの世界情勢の空気感を知ることのできる貴重な一冊になっている。 |
|
|
日本の教科書では戦後のどたばたで年表ぐらいしか出てこない朝鮮戦争だが、朝鮮半島を巡って米国・中国・ソ連のそれぞれの立場が明確化した戦争として一体当時にどういったパワーバランス下でこの戦争は発生し、そして終了したのかは朝鮮半島情勢を考える上で絶対に知っておきたい。 |
|
|
経済と政治体制は密接に関わっており、投資において政治が安定している国が好まれることがよくわかる一冊で、経済・政治・投資の関係性を勉強していると必ず一度は読む一冊。 |
|
なぜ大国は衰退するのか ―古代ローマから現代まで |
大国の勃興と没落までを歴史を通じて学べる推薦図書のうちの一冊。今の米国も今すぐではないが、超大国の座をいつまで守れるのかを考察するのに役立つ一冊だと思う。 |
|
アフリカ地域への投資はまず利益にならないことがわかる一冊。法があってないようなもの・常に暴力と破壊に怯えてはビジネスはまともにできないということがよくわかるし、そんな状態では外国人投資家は継続的な投資をしてくれない。 |
|
|
中東の地政学がいつまでも安定しないことについて、サイクス=ピコ協定だけでなくもっと根本的な原因について深く洞察した書籍で、中東の地政学について知っておくべきことが書いてある良書。 |
|
|
|
中東の地政学の歴史だけでなく、イスラム教自体がどのような論理構造・思考で文化が構築されているかがわかる一冊で、中東で起こる不思議な民衆の反応を理解する上では必須な一冊。 |
|
米国側からみた日本に期待する役割と、実際に日本をどう使っていくかをあけすけに書かれている書籍で、米国が歴史的に日本をどのような観点で見ているかを知ることのできる推薦図書。 |
|
|
毛沢東時代から鄧小平時代への変遷の中で、どのように中国で資本主義が発達してきたか、マクロからミクロまでの分析を通じて分析した中国資本主義の歴史書として非常に参考になる書籍。中国人の起業熱が高いこともこの書籍を読めばわかると思う。 |
|
|
人類がここまで発展していく過程でエネルギー消費はどのように変化してきたかわかり、今後の投資を考えていく上での一助になると思う一冊。 |
|
|
|
投資において紛争が与える影響が大きくなっている昨今、紛争はどのような地域でどのような原因で発生しているのか理解するのは、国際的な投資をする上で重要な第一歩として使える書籍。 |
現代地政学 国際関係地図 |
ざっくりと世界の地政学リスクの歴史と現在どういった地域で地政学リスクが存在するのかがわかる一冊で、地政学リスクを把握する初歩的書籍として推薦したい。 |
プーチン 〔外交的考察〕 |
クリミア併合らへんのことが詳しく書かれており、2022年ウクライナ侵攻をなぜプーチンは決断したのかのヒントが得られる一冊。その他ロシア外交の基本的考え方や政治をおさらいしておくのには必読といっていい一冊。 |
|
|
現代の国家構築はどのような考え方で構成されているか、特にナショナリズムという点にフォーカスして書かれた、E.H カーの名著。 |
危機の二十年-理想と現実 |
国際政治はユートピアニズム(理想・道義)とリアリズム(現実論・国家間パワー)の狭間でバランスを取りながら考えるべきもので、どちらかに偏った時に大きく政治バランスを崩して政治体制が混乱を極めることを書いた名著。 |
|
|
中国の台湾侵攻の可能性を考える上で、金門島の立ち位置を再確認することができる書籍。 |
|
|
第二次世界大戦以降の米国の基本的な地政学に対する対処手法を書いた書籍で、現在の米中・米ロ関係の先行きを考える上で参考になる書籍。 |
|
|
アフリカはやはり国としての歴史や文化が浅く、権力者が易きに流れてしまうために発展の糸口を掴めないんだなということがわかる。 |
| 新興国投資するならアジアに限る理由はグローバルバリューチェーンに乗っかってる新興国がアジア地域にしかないからであることが非常に理解しやすい良書。 | |
| 原油価格の低迷は2016年からずっと続いているが、その背景や原油価格の分析初歩を学ぶのに推薦したい書籍は下記になります。ちなみに著者の岩瀬昇氏は元ライフネットの岩瀬大輔氏の実父です。 | |
|
ピーターティール氏の起業&投資哲学書。数々の起業とエンジェル投資の成功からどのようなどういった企業が大きくなるかについての考察が余すことなく書かれている。時価総額が小さい企業に投資する人はぜひとも読んでおくべき。 |
|
|
中国人と日本人の国民性の違いを克明に書いた書籍で、非常にわかりやすい。特にビジネス面でのやり方の違いはこの性格の違いが浮き彫りになっているのでこういう違いを理解していると中国株投資するにおいて役に立つと思う。 |
|
 ソフトバンク「常識外」の成功法則 |
孫正義氏の元側近が書いた書籍で、孫正義という人間がどういう人間かを第三者の目で見た書いた書籍。著者曰く孫正義氏は太陽と同じで近づきすぎると焼き尽くされ、適度な距離感があると適温でいいだそうで(笑) |
コンピュータはなぜ動くのか 第2版 知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識 |
IT銘柄が株価を大きく伸ばす中で、そもそもコンピューター自体がどのように動くのかを丁寧に解説した書籍。特に重要基幹部品については知っていると銘柄選択においても役に立つため、ぜひとも読んでおきたい一冊。 |
|
半導体の会社として長い歴史を持つインテルの産業史は半導体関連銘柄に投資する上では知っておきたい歴史が大量に書かれているので読んでおきたい一冊。 |
|
2030 半導体の地政学 戦略物資を支配するのは誰か |
半導体についてグローバルな力関係と、各大手半導体企業がどういう位置づけにいるのかわかる書籍であり、半導体銘柄に投資するなら一度は絶対に読んでおきたい書籍。 |
|
ちょうど世界的に製造業が水平分業され始めて半ばぐらいに出版された本で、今では古典的なグローバル経済のあり方について考える書籍の一つなので、まだ読んだことがない方はぜひとも読んでおきたい。 |
|
ITロードマップ |
NRIがまとめた最新IT動向と具体的な企業名・案件などを紹介しており、IT動向全然わからないけどIT銘柄投資のヒントを得たいと思った時に読みたい一冊。毎年新しい動向を追った新刊が出るのも嬉しい。 |
|
身近に利用しているサービスのアルゴリズムの仕組みが理解できる良書。特にグーグルのアルゴリズムの仕組みについて理解できるのはとても良いと思う。 |
|
|
コンテナという共通規格が飛躍的に世界の物流効率を上昇させたという話。産業革命以降、如何に世界的な共通規格というのが重要なのかがわかる一冊。 |
|
|
戦後から米国市場へ本格進出する手前までにおける現場カイゼンの歴史をつづった書籍で、戦後の焼け野原からいかにして米国自動車会社と闘って勝つかを現場の労働生産性改善に見出して、トップが真剣に現場を見ながらトヨタ生産方式を確立させていった話。 |
|
世界国勢図会 |
コモディティ毎の基本的な世界各国のシェアが時系列でまとめられており、1年ごとぐらいにコモディティの基本情報のアップデートをする上で非常に有用。 |
|
|
昨今の新興国経済の勢いがないことに脱工業化が早すぎることが書いてあって、なかなか現在の新興国が先進国に追いつくことは難しくなりつつあることがわかる一冊でお薦め。新興国株に過剰な期待を持っている人にまず読んでもらいたい。 |
|
|
かつて栄華を極めた米国大手企業GEがどのように崩壊に至ったかを書いた書籍で、米国企業の典型的な失墜例として非常に参考になる。トップダウンによる無理な経営目標・無茶な結論ありきの買収などのガバナンスの欠如からセクター丸ごと逆風を受けてどうしようもなくなったら米国企業はあっさり倒れるのがわかる。 |
ネット興亡記 敗れざる者たち |
サイバーエージェント・楽天・ライブドアなど2000年代で興った日本のIT企業の裏話が盛りだくさんなのと、各社がどのような関係にあったのかがわかる一冊で、一つの歴史書といってもいいかもしれない。 |
|
|
日本国内大手運用会社のESGに関する基本的な取り組み方がまとめられていて、業界関係者なら必読といった内容になっている。 |
図解インド経済大全 全11産業分野(73業界) |
ポスト中国としてインド株に注目が集まる中、主要な上場インド銘柄の紹介がされていて、どういった市場でどのような上場大企業が存在するか一目でわかる書籍なので、インド株に興味がある方は読むべき書籍だと思う。 |
|
|
インド株にすごい希望を見出している人もいるが、今一度本当にそれでいいのかどうなのか冷静に考えされられるきっかけになる本だと思う。 初っ端から最大級財閥のリライアンスに切り込んでいることに加えて、昨今問題になったアダニグループと政治の近さについても解説がなされている。 |
|
|
世界の主要なVCファンドとその投資哲学がわかると同時に、2020~2021年に過剰流動性相場の中で馬鹿みたいなバリュエーションがついてその後次々と死んでいった新興銘柄群一覧を確認できる、ある意味歴史書に近いものを感じる。 |
フェイスブックの失墜 |
フェイスブックの飛躍はなぜ躓き、一時期株価が暴落したのかがわかる一冊。若く急成長してきた企業にありがちな、内部統制・コンプライアンス対応が皆無に近い状況で社会的影響力を持ったせいで、スタートアップから大企業へ変化する際に慎重な移行を行わないと大きな痛みを伴うことがわかる。 |
|
|
輝かしいスタートアップ企業であるウーバーの回顧録的な書籍。ウーバーがどのように台頭し、その後失墜していったのかがわかる一冊だが、それと同時に当時の低金利環境下で社会的に受任することのできないパワハラ・セクハラ体質を無視して拝金主義的に資金を提供したシリコンバレーのPE・VCの功罪と、自分が神だと勘違いした成長しているスタートアップ企業の文化が理解できる。 |
デマの影響力――なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか? |
SNSビジネスの問題点を浮き彫りにした書籍で、SNS上で起こる大体の問題が網羅されている。これを読むと、どうもSNSビジネスは今後(2023年現在)かなり難しいコントロールが要求されるため、投資先としてはかなり難しいことがわかる。 |
|
|
米国のシェールガス革命が起こるまでのドキュメントで、構想自体は1980年代からあり、長い時間をかけ数多の挑戦者が起こしたイノベーションであることがわかる一冊。ローマは一日にしてならずとはまさにこのことだと思う。 |
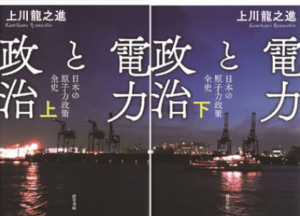
電力と政治 (全2巻) |
戦後~高度経済成長期~東日本大震災~その後の原発再稼働までの電力会社と政府の関係を中立的に書いた書籍で、電力株投資を考える上で参考とするべき一冊だと思う。 |
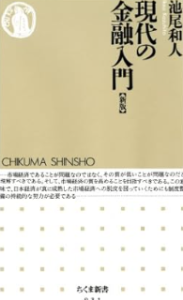 |
金融の基礎知識として知っておくべき事柄が網羅された良書なので推薦。とりあえずこの一冊読むだけで金融の存在意義とは何かいう基礎知識は網羅できていると思う。 |
 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式 |
オプション価格の計算では必須のブラックショールズ方程式について、一応それっぽく理解しておきたいという人向け。 |
| こちらもデリバティブ価格の算出方式であるマルチンゲールアプローチを解説する書籍でややアカデミック寄りだが、実務家なら一度読んでおきたいところ。 | |
| 株式投資は基本的には債券・金利の上に浮かぶ小島であり、債券関連はどのような投資戦略が存在していているのかを知っているだけでも有用。なお、これから債券運用やりますという駆け出しプロの方はまずこれを読むことになります。 | |
| コロナ禍で米国政府が財政政策を実施して景気を持ち上げているのは、まさにこのMMT理論的なものであり、実質的にMMT理論を実施しているので頭に入れておきたいところである。 | |
| 過去の国家のデフォルト事例と定性的な面と定量的な面の両方の側面から書いた、アカデミックな部分と実務面を織り交ぜて書いた書籍。新興国ソブリンとかに投資する人は一度読んでおいておきたい書籍だと思う。 | |
| 古典的経済学のケインズ氏の勉強をせずに現代経済学を考えることは難しいので、きちんと経済学を勉強しておきたい方はケインズ氏の理論ぐらいは勉強しておきましょう。 | |
| 一般的な各種スワップ取引を網羅しているだけでなく、通貨ベーシス・EB債のバリュエーション計算方法・OISカーブからの政策金利予想などかゆいところに手が届く解説書で、プロなら読んでおきたい一冊。 | |
| 産業革命期から現代AIまでの間のテクノロジー進化・政治体制の影響・雇用問題についてまとまっている。特に昨今のITによる一部職の消滅による雇用悪化は産業革命直後の状況と似ているというのは知っておくべきところ。 | |
| 一通りの金融工学で知っておかなければいけない理論と計算方法について書かれている書籍で、とりあえず基礎的な知識を網羅的に一回さらいたかったらこの一冊だと思う。 | |
2023年からのバーゼルIIIQ&A |
金融規制絡みの話はこの一冊をしっかり読み込めばよいと思う。ここらへんをきちんと理解せずに銀行株投資とか金融社債投資とかはあり得ないと思う。 |
物価とは何か (講談社選書メチエ) |
日本において物価研究で名が知られているNowcastの渡辺氏の著書。 物価は蚊柱のようなものという話や、物価には様々な計測方法があり未だ議論になっていること・中央銀行の役割などについて学術的な話+実務的な行動も交えながら書いており、物価に対するアプローチを考える上で一度は読んでおきたい。 |
金融正常化へのジレンマ |
今まで読んだ書籍の中ではきちんと論理立って日銀の異次元緩和の問題点についてまとめられているので、きちんと問題点についてまともに整理したい人は下記書籍を読むのがお薦め。 |
国際収支の基礎・理論・諸問題―政策へのインプリケーションおよび為替レートとの関係 |
新興国投資する上で絶対に理解しなきゃいけない国際収支の基礎的な考え方と過去の危機事例がしっかり書かれていて、概ね基礎知識はこの一冊でよいと思う。 |
金融危機とバーゼル規制の経済学 |
リーマンショックが発生したメカニズムを表面的な話ではなく、きちんと金融実務に即して詳しく書いていったもので、どれだけ金融市場に自分が詳しくなっているか理解するための確認的な形で使える。 ここに書かれてある内容が全て理解できるなら、プロ並みといって間違いない。 |
|
|
日本国債が金利ある世界に戻りつつある中で、日本国債市場・取引の理論および実務について真剣に学ぶべきタイミングが来ていると思うが、過去2009~2021年の間は金利のない世界だったのでまともな書籍がなく、これが一番最新かつ理論だった書籍となっている。 |
| 機械学習やクオンツをどのように投資手法に落とし込むかの基礎的な例を書いてある一冊。これ自体でクオンツファンドができるというわけではないが、初歩の初歩を知りたいという方は読んでおきたい。 | |
| Pythonの基本的な使い方とデータ分析のやり方について実コードを用いながら解説しているので、初心者の方にはとっつきやすい一冊。ProgateでのPython学習とあわせて勉強すると知識習得がはかどる。 |
|
「1秒!」で財務諸表を読む方法 ―仕事に使える会計知識が身につく本 |
財務分析を今までしたことがないという方が最初に読んで勉強してもいいかなと思える書籍で、自分もここらへんから最初は勉強のために読み始めた。 |
 よくわかる格付けの実際知識 |
格付け会社が実際にどのような観点から格付けを付与しているのかがわかる一冊で、知識を積んで格付け比較をしていけば大体自分なりに企業の財務に関する危険性がぱっとみてなんとなく把握することができるようになる。 |
|
やや古い書籍だが、大手格付け機関であるムーディーズが格付け分析手法について事細かく余すことなく手法を記載した辞典並に分厚い書籍。格付け機関がどのように財務分析をしているかを本当に知りたいならこの一冊は絶対に読みたい。 |
|
いわゆるマンションを買うときは「管理を買え」と言われているが、どういった部分を見ればいいか現役の大手不動産会社の人が書いているので、これからマンションを買おうと思う人は一度読んでみるといいと思う。 |
|
|
不動産投資している人の間で有名な書籍。エクセルで不動産投資の収益を数字としてどのようにシミュレーション・管理をし、どれだけのリターンを測れるかの計算の仕方について丁寧に書かれている。なんとなくではなく、きちんと数字で不動産でどれだけリターンを出せるか計算をやってみたいという方向け。 |
|
|
向こうからやってくる不動産は全部クソという名言を生んだ一冊。少なくともこんな不動産投資に騙されるぐらいなら最初からやるなというのがわかる。 |
|
|
不動産投資において気を付けるべき項目がほぼ全て網羅されている良書で、不動産投資を行う前に絶対に読んでおきたい一冊。 |
|
|
不動産投資において収支をどうエクセルで計算するかがわかる一冊で、初心者は不動産業者の収支シミュレーションを鵜呑みせずにきちんと自分で収支シミュレーションを計算して投資を実践してほしい。 |
|
数あるグーグルの働き方書籍の中で、グーグル社内で唯一認められている書籍。逆に言うとこれ以外のグーグル働き方書籍は全部偽物という扱われ方になっている。 |
|
|
投資とは無関係だけど、プレゼンとかでいかに見栄えよくしゃべるかというので、どういうことを会得すればつまることがなくなるかのノウハウがつまっているのでおすすめ。 |
|
|
この書籍自体はコロナ禍前に発売されたものだが、コロナ禍以降はこの書籍に書いてある働き方が是とされる流れが一気に強まったように感じる。ただし、あくまで「こういう働き方ができるぐらい有能な人」という前提がある。 |
|
|
V字回復経営と書いてあるが、実際は日本電産流の科学的手法を用いた営業手法をメインで書いた書籍。根性論営業からより系統立った営業アプローチをしたいと考えているビジネスマンに推薦したい。 |
|
「クビ!」論。 |
米国流のリストラはどのように行われるかがよくわかる一冊で、米国企業を見る上で素早いリストラがこのように断行されるのだなと実感できる一冊。 |
アイデア大全 |
アイデア出しに詰まった時に使える古今東西のアイデアひねり出し手法を書いたもの。 |
|
|
パーソナリティ障害的な政治家がなぜ台頭するのか、そして台頭すると何が起きるのかを書いた書籍で、こうした悲惨な事態を防ぐために民主主義があるんだなと感じさせる一冊。 |
|
|
相場には人を魅了する魔力があると思ってり、それはカジノに非常に似ている。そしてカジノに魅了された人達は破産すべくギャンブル依存症にかかり、全てのお金を吐き出すわけだが、そういう人達の心理を知れば相場で勝つヒントがあるのではないか思う。 |
|
|
一見投資と関係なさそうな書籍だが、投資を行う上で人間の特性が合理的な行動を色々な形で阻害していることがわかる書籍で、より深く投資を考える上では有用でした。 |